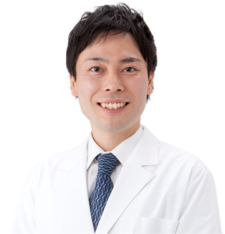「最近、咳が止まらなくて困っているんだけど…」 「夜になると急に咳が出て、なかなか眠れない…」 そんな悩みを抱えていませんか? 実は、これらの症状は単なる風邪ではなく、「咳喘息(せきぜんそく)」かもしれません。咳喘息は、その名の通り「咳」が主な症状として現れる病気です。風邪のような咳と違って、3週間以上も長く続くことが特徴です。 診断基準としては8週間以上咳が続くものと定義されています。
この記事では、咳喘息とはどんな病気なのか、どんな症状が出るのか、そしてなぜ咳が長引いてしまうのかについて、詳しく解説していきます。ご自身や家族の症状が咳喘息かもしれないと気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1. 咳喘息ってどんな病気?

私たちが普段、風邪をひいた時の咳は、だいたい1~2週間で良くなりますよね。しかし、咳喘息の場合は「長い間咳が続く」というのが大きな特徴です。 咳喘息は、一般的な喘息(ぜんそく)の仲間です。しかし、普通の喘息でよく見られる「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という音はほとんど聞こえません。代わりに、からからとした乾いた咳が続くのが特徴的です。 実は、長引く咳の原因として最も多い病気の一つなのです。 特に以下のような特徴がある場合は、咳喘息の可能性を考えてみる必要があります。
- 夜になると咳が多くなる
- 寒い空気を吸うと咳が出やすい
- 運動をすると咳が出る
- 市販の咳止め薬があまり効かない
では次に、なぜこのような症状が起こるのか、体の中で何が起きているのかを詳しく説明していきます。
2. 体の中で何が起きている?咳喘息のメカニズム
咳喘息は、私たちが呼吸をする時に使う「気道」で起こる病気です。特に気道の入り口付近に炎症が起きることで、咳が止まらなくなってしまいます。 どうして炎症が起きると咳が出るのでしょうか?これを理解するために、まずは健康な人の気道の仕組みを見てみましょう。
【健康な気道の場合】
- 気道の内側は、とても薄い粘膜で覆われています。
- この粘膜は、外からの刺激(ほこりや冷たい空気など)から体を守っています
- 普段は適度な潤いがあり、外からの刺激にも程よく反応します
【咳喘息の人の気道の場合】
- 気道の入り口付近の粘膜に炎症が起きている
- 粘膜が腫れて、とても敏感になっている
- ちょっとした刺激でも敏感に反応して、咳が出てしまう
例えると、健康な気道は「丈夫なガードレール」。しかし、咳喘息の気道は「傷ついて敏感になったガードレール」のような状態なのです。そのため、普通の人なら気にならないような刺激でも、すぐに咳という形で反応してしまいます。 では次に、この敏感になった気道がどんな時に反応しやすいのかを見ていきましょう。
3. どんな時に咳が出やすくなる?
咳喘息の方の気道は、とても敏感になっているため、様々な刺激で咳が誘発されやすくなっています。特に以下のような時に咳が出やすくなります。
【気温の変化で】
- 寒い外気を吸い込んだ時
- 暖かい部屋から寒い場所に移動した時
- エアコンの冷たい風を直接受けた時
【空気の状態で】
- 乾燥した空気を吸った時
- タバコの煙を吸い込んだ時
- 強い香りのある場所にいる時
【体を動かした時】
- 運動をした時
- 階段を上った時
- 急いで歩いた時
そして、咳喘息の最も特徴的な症状が「夜に咳が悪化する」ということです。なぜ夜になると咳が多くなるのでしょうか?
4. なぜ夜に咳が多くなるの?
夜になると咳が悪化するのは、咳喘息の大きな特徴です。実は、これには私たちの体の自然な仕組みが関係しています。
【体温の変化】
私たちの体温は、夜になると自然に下がります。体温が下がると、気道も冷えて少し縮むような状態になります。この変化が敏感になっている気道をさらに刺激してしまうのです。
【寝る姿勢の影響】
横になって寝ることで、気道の形が変わります。特に横向きに寝ると気道が少し押されたような状態になり、咳が出やすくなってしまいます。
【体を守る力の変化】
私たちの体には、炎症を抑える物質が作られています。しかし、この物質は夜になると少なくなってしまいます。そのため、気道の炎症が悪化しやすくなるのです。
【寝室の環境】
- エアコンや暖房で空気が乾燥している
- 寝室の温度が低すぎる
- 寝具からのホコリが舞っている
これらの要因が重なることで、夜間に咳が悪化してしまうのです。夜に咳が多い方は、寝る前の部屋の環境を整えることが大切です。
5. 敏感になった気道との上手な付き合い方

咳喘息の原因となっている敏感な気道は、適切なケアをすることである程度症状を和らげることができます。
【温度と湿度の管理】
気道は温度と湿度に敏感です。特に就寝前の環境づくりが大切です。部屋の温度は18~22度程度、湿度は50~60%程度に保つことで、気道への刺激を減らすことができます。
【刺激を避ける工夫】
気道が敏感になっているときは、できるだけ刺激を避けることが大切です。例えば、
- マスクの着用で寒い空気を和らげる
- 急な温度変化を避ける
- 香りの強い製品は控えめにする
ただし、これらの対策はあくまでもセルフケアの一部です。咳喘息の本格的な治療については、医師による適切な診断と治療が必要です。
まとめ:咳喘息の仕組みを理解しよう
ここまで咳喘息の仕組みについて詳しく見てきました。重要なポイントを整理しておきましょう。
【咳喘息の特徴】
- 気道の入り口付近に炎症が起きる病気
- からからとした乾いた咳が特徴
- 3週間以上咳が続く
- 夜間に症状が悪化しやすい
【咳が出やすい状況】
- 寒い空気を吸い込んだ時
- 運動をした時
- タバコの煙や強い香りがある時
- 急な温度変化がある時
これらの症状が当てはまる方は、咳喘息の可能性があります。特に夜間の咳で眠れない、長期間咳が続くといった症状がある場合は、医師に相談することをおすすめします。
次回は、咳喘息と間違えやすい病気について詳しく解説します。咳の特徴の違いや見分け方のポイントをご紹介しますのでぜひご覧ください。
お問い合わせ >>
お電話でのお問い合わせ >>
TEL.06-6147-4400