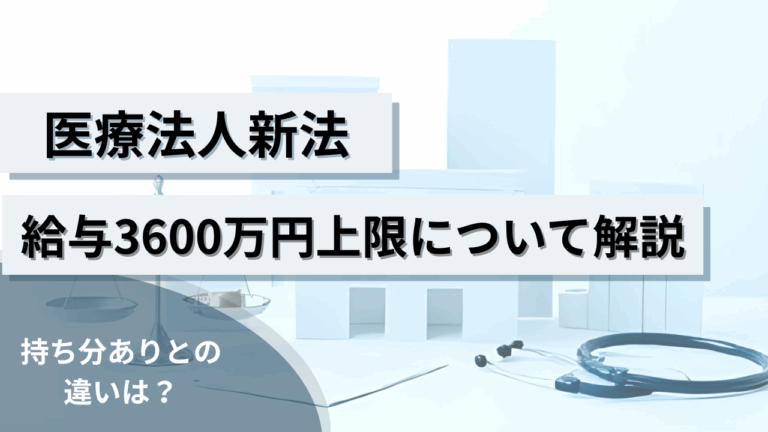税理士から「医療法人は新法対応を考えた方がいい」と言われ、不安を覚えたことはありませんか。普段は気にしない話でも、専門用語が出てくると急に現実味を帯びるものです。
とくに「持分は相続できない」「相続税が重くなる」と聞くと、自分の法人も該当するのでは…と心配になる方は少なくありません。もし突然の事態が起きたら家族はどうなるのか、その点が気になるのは当然です。
では、新法と旧法では何が違い、なぜ“持分が相続できない”と言われるのでしょうか。旧法のままでいることにどんなリスクがあるのでしょうか。
本記事では次の内容をわかりやすく整理します:
- 旧法(持分あり)と新法(持分なし)の構造的な違い
- 新法移行で相続できなくなる理由
- 出資持分の相続税評価が高くなりやすい背景
- 新法移行のメリット・注意点
- 親族承継や第三者承継で押さえるステップ
読み終える頃には、あなたの医療法人が「今なにを検討すべきか」が明確になります。家族とクリニックを守る判断材料として、安心して読み進めてください。
目次
「持分あり/持分なし」「旧法/新法」とは
医療法人の相続や承継を理解するためには、「持分あり/持分なし」と「旧法/新法」の違いを押さえることが重要です。制度改正により、医療法人の財産権の扱いは大きく変わりました。
まずは、出資持分という基本概念と、旧法から新法へ移行する背景を簡潔に整理します。
医療法人における「出資持分」とは
出資持分とは、医療法人に出資した人が持つ「財産的な権利」のことです。退社時の払戻請求や解散時の残余財産分配を受けられる点が特徴で、相続の対象にもなります。
一方で、法人側は持分払戻しに備える必要があり、相続税評価も高額になりやすい仕組みです。
「持分あり医療法人(旧法型)」と「持分なし医療法人(新法型)」の定義・法令上の位置づけ
旧法型は、出資者に財産権が残る「持分あり」の医療法人です。相続・贈与の対象となる一方、法人の非営利性との整合が課題となってきました。
新法型は、平成19年以降に設立された「持分なし」の医療法人で、出資者の財産権を認めない仕組みです。公益性を高める目的で導入され、解散時の財産は公共性の高い主体へ帰属します。
参考リンク:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000084153_3.pdf
旧法から新法への移行の経緯と「経過措置型医療法人」の概念
平成19年の法改正により、新しく設立できるのは原則「持分なし」のみとなりました。一方、改正前の持分あり医療法人は「経過措置型」として存続が認められています。
その後、持分あり法人が円滑に「持分なし」へ移行できるよう、移行計画の認定制度や税制優遇が整備されました。現在は、旧法から新法への移行を促す政策が進んでいます。
医療法人の新法と旧法の根本的な違いを理解する
医療法人の相続対策を考える際、まず理解すべきなのが「旧法=持分あり」「新法=持分なし」という構造の違いです。これは単なる呼び名の違いではなく、“相続できる財産が存在するかどうか”に関わる本質的な違いです。
ここでは、財産権の扱い、相続対象の違い、そして政策的に新法移行が進められてきた理由を整理します。
持分あり(旧法)と持分なし(新法)の法的構造の違い
旧法型医療法人では、出資した額に応じて「出資持分」が認められ、出資者は退社時の払戻請求や解散時の残余財産分配を受ける権利を持ちます。これは株式に近い“財産権”であり、個人の資産として評価されます。
一方、新法型では出資者に財産権がありません。出資は法人への寄付に近い扱いになり、法人の純資産としてのみ計上されます。解散時の財産は公益性の高い団体に帰属させる必要があり、個人に分配される仕組みではありません。
つまり、旧法=財産権を伴う構造、新法=財産権を切り離した構造という根本的な違いがあります。
相続・承継の対象になるもの/ならないものの違い
旧法型では「出資持分」が相続の対象になります。相続税評価は法人の純資産額を基に計算されるため、現預金が多いクリニックでは高額評価になりやすい特徴があります。相続人はその評価額に応じた相続税を現金で支払う必要があり、納税負担が大きな問題になりやすいのが実情です。
新法型では、そもそも出資額に応じた財産権が存在しません。そのため、相続の対象となる“持分”が消滅します。受け継がれるのは法人の「役職(理事長など)」であり、財産そのものではありません。
つまり、新法では財産の相続ではなく、経営権の承継が中心になる点が重要です。
新法移行が全国で進む背景と政策的意図
旧法型では、相続税の高額化や、退社時の持分払戻しによる資金流出が問題となり、「地域医療の継続に支障が出る」と懸念されてきました。また、医療法人は本来「非営利性」が条件であるにもかかわらず、実態としては個人の財産形成手段になりやすい面が指摘されていました。
こうした背景から、厚生労働省は平成19年以降、持分なし医療法人のみ新設を認め、既存の持分あり法人には移行制度・税制措置を整備して新法化を促しています。
政策的には、非営利性の明確化・相続トラブルの回避・法人経営の安定化が目的であり、結果として新法移行が年々進む状況にあります。
参考リンク:https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000951888.pdf
新法移行で「相続できない」と言われる3つの理由
医療法人の新法移行を調べると「持分は相続できない」と必ず目にします。これは決して曖昧な表現ではなく、法制度の構造が“相続そのものを不可能にしている”ためです。
ここでは、なぜ新法型に移行すると出資持分が相続できなくなるのか、その根拠を3つの視点から整理します。
持分概念が消滅し「財産権としての出資」がなくなるため
新法型(持分なし医療法人)では、旧法型に存在した「出資持分」という財産権そのものが制度的に認められていません。
厚生労働省の制度説明でも、持分なし医療法人では出資に対して払戻請求権や清算時の残余財産請求権が存在しないことが明記されています。
つまり、新法型にはそもそも相続の対象となる「財産権」が存在しません。
- 旧法型=出資持分に財産権あり(出資持分は相続対象)
- 新法型=出資持分としての財産権なし(出資持分については相続対象がゼロ)
という構造的な違いにより、結果として「持分は相続できない」という結論になります。
出資者個人の権利が法人に帰属するため
新法型では、出資によって形成された財産は、出資者個人ではなく「法人そのもの」に完全帰属します。このため、出資した個人が退社しても財産返還はなく、解散時の財産分配も認められません。
医療法人は非営利法人であることが前提とされており、新法型はその原則をより明確にした仕組みです。
法人の財産=出資者個人の財産ではないため、権利が個人に紐づかず、死亡時に相続として承継される“個人財産”に該当しなくなります。
相続税対策として制度が統一されつつあるため
旧法型医療法人では、出資持分が「個人の財産」として扱われるため、相続税評価の対象になります。純資産が多い法人ほど評価額も高くなり、多額の相続税が発生することが全国的な問題となっていました。
こうした背景から、国は“医療法人を個人資産の形成手段にしない”という方向性を強め、新法型への移行制度・税制優遇を整備しています。
政策的にも「相続税リスクを制度から切り離す」ことが求められ、新法型=持分なしという仕組みが標準化されつつあります。
旧法(持分あり)医療法人における出資持分の相続税評価の仕組み
旧法型の医療法人では「出資持分=相続財産」として扱われ、相続が発生すると高額な評価額が算出されることがあります。
ここでは、評価方法の原則と、医療法人の資産構造が評価額に与える影響、そして実際にどの程度の相続税負担が生じるのかをイメージしやすい形で整理します。
純資産価額方式による評価と膨らみやすい理由
旧法型医療法人の出資持分は、原則として「純資産価額方式」で評価されます。これは、(総資産 − 負債)=純資産 を基準とし、持分割合を掛けて算定する方式です。
医療法人は事業上、現預金や設備資産を多く保有する傾向があるため、純資産額が大きくなりやすく、結果として評価額が膨らむ特徴があります。
特に、開業から年数が経過し法人内に現金が積み上がっている場合、持分の評価額が想像以上に高額になるケースが少なくありません。
※評価方法は国税庁「財産評価基本通達」に基づき算定されます。
医療法人特有の資産構造(現預金・不動産・設備等)の影響
医療法人は、診療報酬の入金サイクルや運転資金確保の必要性から、一般企業よりも現預金が多い傾向があります。
さらに、医療機器やレントゲン設備などは簿価が大きく、減価償却が進んでいない場合は資産額が高く計上されます。
また、建物や土地などを法人名義で保有している場合、これも純資産価額を押し上げる要因になります。これらの資産構造が積み重なることで、「評価額 > 実際に処分できる価値」になりやすい点が医療法人の特徴です。
相続税額の概算イメージと数値例
出資持分の評価額は、純資産の規模に応じて大きく変わります。例えば、純資産が2億円ある法人で、持分割合が100%の場合、評価額は2億円となります。
相続人が子1人として、基礎控除などを考慮しても、税率30〜40%台が適用されることがあり、6,000〜8,000万円前後の相続税が発生するケースも珍しくありません。
重要なのは、この税金を現金で納める必要があるため、法人に資金があっても相続人の手元に現金がなければ納税に困るという点です。結果として、医院の売却や借入が必要になる事例が全国的に報告されています。
出資持分の評価額が高額化しやすい医療法人の3つの特徴
旧法型医療法人では、出資持分が「純資産価額方式」で評価されるため、法人の資産構造によっては相続税額が極端に増えるケースがあります。
ここでは、特に評価額が膨らみやすい医療法人に共通する3つの特徴を整理し、なぜ相続税リスクが高まりやすいのかを分かりやすく解説します。
現預金が積み上がりやすい経営構造
医療法人は、診療報酬支払いの仕組み上、一定の運転資金を持つことが求められます。また、長年の黒字経営により、現預金が法人内に蓄積されやすい傾向があります。
純資産価額方式では 現預金=そのまま評価額に反映 されるため、現預金が多いほど出資持分の評価も直線的に上昇します。
加えて、医療法人は内部留保を積み上げても株主配当のような分配ができず、結果として資金が法人内に滞留しやすい構造が相続税評価の高さにつながります。
設備投資後の簿価と市場価値の乖離
医療機器は高額な設備が多い一方、中古市場の流通が限られており、実際に売却価値は低くなりがちです。しかし、帳簿上は一定期間にわたって減価償却されるため、簿価が実際の市場価値よりも高く残るケースが一般的です。
この帳簿上の価値(=資産計上額)が純資産に反映されるため、市場価値より高く評価される結果、出資持分の評価額が膨らむ原因となります。
法人内留保が多く「評価額>実態価値」になりやすい構造
医療法人は非営利法人であり、利益を出しても個人に分配できません。したがって、利益が積み重なるほど法人内留保が増え、純資産が年々増加します。
一方で、医院を実際に第三者へ売却する場合、医療法人そのものの譲渡は不可であり、事業承継やM&Aは設備や患者基盤など別の評価方法が用いられます。
そのため、帳簿上の純資産価額と実態価値には大きな差が生じやすく、**「相続税評価だけが不合理に高くなる」**という典型的な状況が発生します。
持分のない医療法人への移行で生じる5つのメリット
旧法型のままでは、相続税負担や親族間の不公平といったリスクが長期的に続きます。そこで、多くの医療法人が検討しているのが「持分なし(新法)への移行」です。持分をなくすことで財産権は消滅しますが、法人運営の安定性や承継のしやすさといった大きなメリットが得られます。
ここでは、特に重要な5つのメリットを整理します。
相続をめぐるトラブル回避(兄弟間の不公平防止)
持分あり医療法人では、相続発生時に「出資持分の取り分」をめぐって兄弟間で不公平が生まれやすく、家族内トラブルの典型例となっています。
持分なしへ移行すると、そもそも出資者個人の財産権がなくなるため、出資持分については相続対象となる財産がなくなります。
結果として、「誰がどれだけ相続するか」という争点が消えるため、親族間の不公平感が生まれにくくなり、承継プロセスが格段にスムーズになります。
相続税負担の大幅軽減
持分あり法人では、出資持分が法人の純資産に基づいて評価されるため、純資産が大きいほど相続税も高額になります。
一方、持分なし法人に移行すると、出資持分そのものが消滅するため、出資持分に係る相続税の対象となる“財産”がなくなります。
その結果、出資持分に関連する相続税負担が大幅に軽減されるケースも多い点が、大きなメリットと言えます。
※他の個人資産に係る相続税は別途発生し得る点には注意が必要です。
法人格の安定と永続性の確保
持分あり法人では、出資者の退社や相続に伴う払戻請求が発生し得るため、法人の資金繰りに影響が出るリスクがあります。
持分なし法人に移行すると、払戻請求権が存在しなくなるため、法人の資金が外部へ流出する心配がありません。
その結果、法人の財務基盤が安定し、長期的に医療提供を継続しやすくなるという大きなメリットが得られます。
親族以外の後継者でも引き継ぎやすい組織形態
旧法型では、持分の承継や贈与が絡むため、基本的に親族以外への承継が難しい構造になっています。
持分なし法人は財産権が存在しないため、後継者は親族に限定されず、医師としての実務能力や法人方針への理解を基準に選任できます。
結果として、優秀な医師へのバトンタッチがしやすくなり、地域医療の質を維持しやすいという利点があります。
M&A・第三者承継のしやすさ向上
医療法人は法人そのものを売却することはできませんが、後継者を迎える“第三者承継”という形が一般化しています。
旧法型では出資持分の扱いが障害となり、買い手側も相続税リスクを懸念して承継に慎重になりがちです。
一方、持分なし法人では財産権の問題がなく、承継の条件設定やガバナンス変更がしやすいため、第三者承継の可能性が大幅に広がるというメリットがあります。
新法移行で押さえるべき4つの注意点(税務・手続き・経営)
持分なし医療法人への移行には多くのメリットがありますが、一方で「税務上の取り扱い」や「手続きの厳密さ」に十分注意する必要があります。移行は一度進めると後戻りができないため、事前の準備と合意形成が欠かせません。
ここでは特に見落としやすい4つの注意点を解説します。
出資持分の放棄(贈与扱い)に伴う税務リスク
持分なしへ移行する際、旧法型で出資者が持っていた財産権(出資持分)は「放棄」する形になります。
この放棄は、税務上「法人への贈与」とみなされる可能性があり、贈与税が発生するおそれがあります。
ただし、厚生労働省の「移行計画認定制度」を利用すれば、一定条件のもと贈与税が非課税または猶予される仕組みがあります。
移行を進める際は、税務署への事前相談や専門家のシミュレーションが必須です。
移行には社員総会の特別決議が必要
新法移行は、定款の全面的な変更を伴うため、社員総会で「特別決議」が必要になります。
これは通常の決議よりも重い要件で、社員の3分の2以上の賛成(定款で別途定めがある場合はその基準)を満たす必要があります。
社員が複数いる医療法人では、意見が揃わないケースや、出資者同士で利害が不一致になるケースもあるため、早い段階で合意形成の場を設けることが重要です。
都道府県への認可申請と審査フロー
持分なし医療法人への移行には、都道府県知事の「認可」が必要です。
申請後は、書類審査・ヒアリング・必要に応じた修正指示など複数ステップを経るため、数か月単位で時間がかかることがあります。
移行計画の内容によっては追加資料の提出を求められることもあり、申請手続きは行政書士・税理士など専門家と連携しながら進めるのが一般的です。
出資者間の合意形成が不十分な場合のトラブル
新法移行では、出資者全員が「持分を失う」ことになるため、理解不足や不満があるとトラブルにつながります。
「自分の財産がなくなるのでは?」という誤解が生まれやすいため、移行の目的・メリット・税務上の扱いを丁寧に説明することが重要です。
合意形成が進まないまま手続きを始めると、反対者が出て特別決議が成立しない、遺留分などをめぐる家族間紛争に発展するといったリスクもあります。
医療法人を親族に継承するときの実務ステップ5つ
医療法人を親族に承継する際は、「相続」と「経営移譲」の両面を整理しながら進める必要があります。特に旧法型医療法人では、出資持分の扱いや相続税負担が大きな論点となるため、準備不足は大きなトラブルにつながります。
ここでは、親族承継を成功させるための5つの実務的なステップをまとめます。
出資持分評価の把握と専門家への相談
まず行うべきは、医療法人の「出資持分評価額」の把握です。評価額は純資産価額方式で算出され、現預金や不動産、医療機器などの資産構造によって大きく変動します。
相続が発生してからでは納税資金の確保が難しくなるため、事前に税理士へ評価額を依頼し、相続税の試算まで行っておくことが重要です。
併せて、移行を検討する場合は医療法人制度に詳しい専門家(税理士・弁護士・行政書士)との連携が必須です。
後継者候補との意思確認と役職移行計画の作成
親族承継では、「誰が後継者になるか」を早期に明確にする必要があります。医療法人は法人である以上、理事長や理事の選任、管理者の手続きなど、役職の承継が不可欠です。
後継者が医療行為を行う場合は医師免許が前提となるため、実際に医業を担えるかどうかの確認も必要です。
また、承継タイミングや役職移行のスケジュールを整理した「承継計画書」を作成して共有することで、親族間の誤解や不安を避けられます。
新法移行の検討(持分なし移行を含む)
旧法型の場合、親族承継と同時に「持分なし(新法)への移行」を検討するケースが増えています。
持分ありのまま承継すると、将来の相続税負担や兄弟間の不公平が続くため、早期に持分を整理してしまう方がリスク管理として適切です。
移行計画認定制度を活用すれば、贈与税への課税が抑えられる可能性があるため、早期相談が望まれます。
金融機関・取引先・スタッフへの説明と合意形成
医療法人の承継では、法人名義の借入やリース契約、地域包括ケアとの連携など、外部との関係が多岐にわたります。
後継者の変更や理事長交代は、銀行取引や契約内容に影響するため、金融機関には早めの連絡が必要です。
また、スタッフに対しても「経営方針は変わらない」「雇用条件は維持される」など安心材料を伝え、承継後の混乱を避けることが重要です。
承継後の経営計画・収益モデルの見直し
承継は単なる「引き継ぎ」ではなく、新しい院長が今後の経営をどう進めるかを明確にするプロセスでもあります。
診療内容、スタッフ体制、設備投資、地域ニーズの変化などを踏まえ、5〜10年を見据えた経営計画を策定することが望まれます。
承継を機に法人内の財務状況を整理し、収益性や設備更新サイクルの見直しを行うことで、法人の持続可能性が高まります。
よくある失敗パターン3選と回避策
医療法人の相続・承継は、専門知識と慎重な判断が求められる分野です。しかし、準備不足や誤った理解により、後悔するケースが後を絶ちません。ここでは、実際に起きやすい3つの失敗パターンと、それを避けるための具体的な回避策を整理します。読者の方が同じ失敗をしないための“チェックポイント”としてご活用ください。
相続税額を把握しないまま放置し、家族が支払えなくなるケース
旧法型医療法人の持分は純資産を基準に評価されるため、法人内に現預金が多いほど評価額は高額になります。
しかし「相続が起きたら考えればよい」と後回しにすると、突発的な相続発生時に数千万円規模の納税資金が用意できず、家族が困窮するケースがあります。
【回避策】
- 生前に「出資持分評価額」を専門家へ依頼する
- 相続税の試算と納税資金の確保方法を検討する
- 必要に応じて持分なし移行の可否を早期に判断する
親族間で持分割合の不公平が発生し、争いが起きるケース
旧法型では、出資額に応じて持分割合が異なることがあり、相続発生時に「誰がどれだけ相続するか」が親族間で争点になりやすい特徴があります。
特に兄弟姉妹が複数いる場合、「出資割合=相続割合」となるため、不公平感が大きなトラブルにつながります。
【回避策】
- 承継する親族を明確にし、他の家族にも説明する
- 持分なし移行により“財産としての持分”を消す選択肢を検討する
- 家族間の合意形成を早めに行い、誤解を残さない
後継者が不在のまま法人存続が難しくなるケース
医療法人の承継は、医師である後継者の確保が前提となるため、計画が遅れると「誰も継げない」という事態に直面することがあります。
後継者が決まらないまま院長が高齢化すると、法人の運営継続が難しくなり、結果的に閉院や事業縮小を余儀なくされる例もあります。
【回避策】
- 早期に後継者候補を確定し、意思確認を行う
- 親族に限らず「第三者承継」も視野に入れる
- 経営支援会社・医療法人承継専門家との連携を検討する
開業リスクと事業承継リスクを比較:独立より「院長就任」という選択肢
医師がキャリアを考える際、「独立開業」か「医療法人の承継」かで迷う場面は多くあります。しかし近年は、事業承継で医療法人の院長として就任する働き方が、リスクと収益バランスの面で注目されています。
ここでは、両者のリスクを客観的に比較しながら、「院長就任」という第三の選択肢の魅力を整理します。
開業・独立に伴う3つの主要リスク(資金・人材・経営責任)
独立開業は自由度が高い一方、初期投資・運営リスクが非常に大きい選択です。まず、開業には数千万円規模の資金(内装・医療機器・運転資金)が必要で、銀行借入の返済が長期間続きます。
次に、人材確保の問題があります。医療事務や看護師の採用は地域ごとに競争が激しく、開業初期は人員が安定しにくい傾向があります。
さらに、集患・経営管理・労務など全責任が院長一人に集中するため、臨床と経営の両立に大きな負担がかかります。
こうした理由から、開業は資金・人材・経営の3つのリスクを同時に抱える重い決断だと言えます。
医療法人承継のリスク(税務・持分・親族調整)との比較
一方、医療法人の承継では“設備投資や集患を一から行う必要がない”という大きな利点があります。
ただし、旧法型の場合は出資持分の相続税、親族間の利害調整、理事長交代の手続きなど独自の課題があります。親族内承継であれば、役職移行や法人のガバナンス整理など、早期の計画立案が不可欠です。
しかし、新法(持分なし)への移行が済んでいる法人や第三者承継の場合、財産権の問題は存在せず、主なリスクは“経営引き継ぎの調整”に集約されます。
開業と比較すると、資金リスク・集患リスクが大幅に軽減される点が特徴です。
経営負担を避けながら裁量を持てる「院長就任」という働き方
第三の選択肢として注目されているのが「院長就任型」の承継です。
これは、既存の医療法人に後継者として参加し、理事長・管理者として運営を担う働き方です。この方式は、医療法人のブランド・患者基盤・スタッフが既に整った状態からスタートできるため、経営の初期負担が圧倒的に少なくなります。
また、新法型であれば財産権の問題がなく、給与・裁量・経営判断に関する権限も法人ごとに柔軟に設計できます。
結果として、「開業ほどのリスクは背負いたくないが、自分の医療方針を形にしたい」医師にとって最適な働き方として選ばれています。
| 項目 | 独立開業 | 医療法人承継 | 院長就任(承継型) |
| 初期資金・設備 | 数千万円規模の資金が必要(内装、機器、運転資金)銀行借入の返済が長期化 | 設備投資や集患を一から行う必要がない | 既存のブランド・患者基盤・設備でスタートできるため、初期負担が圧倒的に少ない |
| 人材確保 | 競争が激しく、開業初期は人員が安定しにくい | 既存のスタッフ(医療事務、看護師)を引き継げる | 既存のスタッフ体制でスタートできる |
| 経営責任・負担 | 集患・経営管理・労務など、全責任が院長一人に集中し、臨床と経営の両立に大きな負担 | 経営引き継ぎの調整、旧法型では持分や親族調整の課題 | 経営の初期負担は少なく、経営判断に関する権限を法人ごとに柔軟に設計可能 |
| リスクの特徴 | 資金・人材・経営の3つのリスクを同時に抱える | 旧法型のリスク(税務・持分・親族調整)がある資金・集患リスクは大幅に軽減 | 財産権の問題がなく(新法型の場合)リスクは経営引き継ぎの調整に集約開業ほどのリスクは負わない |
| 自由度・裁量 | 自由度が高い | 役職移行やガバナンス整理が必要 | 給与・裁量・経営判断に関する権限を柔軟に設計でき、自分の医療方針を形にしやすい |
まとめ
医療法人の相続や承継を考える際、「持分あり(旧法)/持分なし(新法)」の違いは最も重要なポイントです。旧法型では出資持分が財産として相続対象となり、純資産の大きさに応じて相続税が高額化しやすい一方、新法型ではそもそも財産権が存在しないため“持分の相続”という考え方自体がなくなります。
また、持分なし医療法人への移行は相続税リスクや親族間トラブルを大きく減らし、法人の安定性を高める有力な選択肢です。ただし、移行には税務・手続き・合意形成といったポイントがあり、専門家の支援が欠かせません。
医療法人を親族に承継する場合も、評価額の把握・後継者との話し合い・移行計画の検討などを早期に行うことで、スムーズで安心な承継が可能になります。
総じて、早めの準備と正確な制度理解こそが、家族とクリニックを守る最良の相続・承継対策です。
※本記事の内容は、執筆時点の制度に基づく一般的な解説です。
具体的な税額や適用の可否は、必ず医療法人に詳しい税理士・専門家にご相談のうえご判断ください。