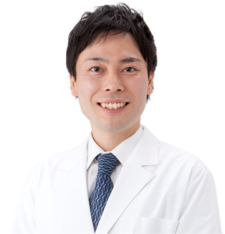「最近、周りで咳喘息になる人が増えているような…」そんな印象を持っている方も多いのではないでしょうか?実は、現代の生活様式や環境の変化により、咳喘息のリスクは確かに高まっているのです。 咳喘息の発症には、年齢や体質だけでなく、生活環境や習慣も大きく関わっているのです。しかし、リスクとなる要因を知り、適切に対処することで、発症や症状の悪化を防ぐことができます。
この記事では、どのような人が咳喘息になりやすいのか、また日常生活のどんな習慣が発症のリスクを高めているのかについて詳しく解説していきます。
目次
1. 咳喘息になりやすい人の特徴とは?
咳喘息は誰でもなる可能性がある病気ですが、特定の体質や特徴を持つ方は、より発症しやすいことがわかっています。まずは、体質や身体的特徴に関するリスク要因を見ていきましょう。
【年齢や性別による違い】
咳喘息は性別や年齢を問わず発症する可能性がありますが、特に30~40代の女性に多く見られます。これには女性ホルモンの影響が関係していると考えられています。また、更年期に入る前後で発症するケースも少なくありません。 咳喘息になりやすい年齢や性別の特徴は以下の通りです。
- 30~40代が最も多い
- 女性の発症率が男性の約2倍
- 更年期前後での発症が目立つ
【アレルギー体質との関わり】
アレルギー体質の方は、咳喘息を発症するリスクが高まります。特に、以下のようなアレルギー疾患がある場合は注意が必要です。
- アレルギー性鼻炎(花粉症を含む)の既往歴がある
- アトピー性皮膚炎の症状がある
- 食物アレルギーを持っている
これは、アレルギー体質の方の気道が刺激に敏感に反応しやすいためです。そのため、通常なら問題にならないような刺激でも咳喘息の症状が引き起こされやすくなります。
【既往歴と基礎疾患】
過去の病歴や持病も、咳喘息の発症リスクに関係します。特に呼吸器系の病気にかかったことがある方は、気道が敏感になっている可能性が高くなります。 気をつけたい既往歴や基礎疾患は以下の通りです。
- 気管支喘息の経験がある
- 小さい頃から気管支が弱い
- 副鼻腔炎(蓄膿症)を繰り返している
2. 要注意!身近な環境に潜むリスク

私たちの周りには、咳喘息の発症リスクを高める環境因子が数多く存在します。日常生活の中で気づかないうちにリスクにさらされていることも少なくありません。
【住環境によるリスク】
家の中の環境は、咳喘息の発症に大きく影響します。特に気をつけたいのは、室内の空気の質です。快適に感じる室内でも実は以下のようなリスクが潜んでいることがあります。
- エアコンによる急激な温度変化
- 暖房による室内の乾燥
- カビや湿気の発生
- ハウスダストの蓄積
特に寝室の環境は重要です。私たちは睡眠中、同じ空気を長時間吸い続けることになるからです。寝具からのホコリやエアコンの風が直接当たることなどもリスク要因となります。
【職場・学校環境の影響】
一日の大半を過ごす職場や学校の環境も、咳喘息の発症に関わる重要な要因です。オフィスや学校での代表的なリスク要因を見ていきましょう。
- 空調設備による空気の乾燥
- 建物の密閉性が高く、換気が不十分
- コピー機やプリンターからの粉塵
- 新築・改装工事による化学物質
特に近年は、オフィスビルシンドロームとして知られる室内環境による健康問題が注目されています。建物の気密性が高まった反面、空気の質が悪化しやすい環境が増えているのです。
【季節や気候の影響】
咳喘息の発症や症状の悪化には季節や気候も大きく関係します。日本の気候は季節によって大きく変化するため、特に注意が必要です。季節ごとの主なリスクは以下の通りです。
- 春:花粉の飛散
- 夏:急激な温度差(室内外の温度差)
- 秋:気温の日内変動
- 冬:空気の乾燥と寒さ
特に季節の変わり目は要注意です。気温や湿度の変化が大きいこの時期は、気道が刺激を受けやすく、咳喘息を発症するリスクが高まります。
3. 生活習慣を見直そう!咳喘息を防ぐポイント

私たちの毎日の生活習慣も、咳喘息の発症に大きく影響します。健康的な生活を心がけることで、リスクを下げることができます。
【喫煙の影響】
喫煙は咳喘息の最も重要なリスク要因の一つです。タバコの煙は気道を直接刺激するだけでなく、長期的な喫煙により気道の防御機能が低下してしまいます。 特に注意が必要なのは、
- 本人の喫煙
- 受動喫煙(家族や職場での周囲の喫煙)
- 過去の喫煙歴
たとえ本人が吸わなくても、周囲の人が吸うタバコの煙を吸い込む「受動喫煙」でも、咳喘息のリスクは高まります。
【運動不足と生活リズム】
適度な運動は健康的な生活に欠かせませんが、運動不足は咳喘息のリスクを高める可能性があります。それは以下のような理由からです。
- 呼吸器系の機能が低下
- 体の免疫力が弱まる
- 気道の粘液線毛機能が低下
また、不規則な生活リズムや睡眠不足も体の抵抗力を弱める原因となり、咳喘息のリスクを高めます。
【ストレスの影響】
現代社会では避けられないストレスですが、実はこれも咳喘息のリスク要因となります。過度のストレスは免疫機能に影響を与え、気道の過敏性を高める可能性があるのです。 ストレスが咳喘息に影響を与える理由
- 自律神経系のバランスが崩れる
- 体の抵抗力が低下する
- 不規則な生活習慣を招きやすい
4. まとめ:リスク要因を知って予防に活かそう
最後に咳喘息のリスク要因について、重要なポイントを整理しましょう。
- 体質や年齢:30~40代の女性、アレルギー体質の方は要注意
- 環境:室内環境や季節の変化が大きく影響
- 生活習慣:喫煙、運動不足、ストレスなどが関係
これらのリスク要因を知ることは、咳喘息の予防の第一歩となります。しかし、すべてのリスクを完全に避けることは難しいかもしれません。 大切なのは、自分に当てはまるリスク要因を把握し、できるところから対策を始めることです。例えば、室内環境の改善や運動習慣の見直しなど、自分でコントロールできる部分から始めてみましょう。
次回は、咳喘息の予防法と日常生活での具体的な対策について詳しく解説します。体調管理のポイントから環境づくりまで、実践的な予防法をご紹介しますのでぜひご覧ください。
お問い合わせ >>
お電話でのお問い合わせ >>
TEL.06-6147-4400